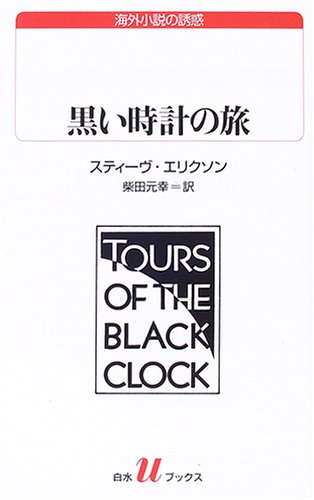柴田元幸印とでもいうか、柴田さんが訳してるんだから間違いないだろうと思って本を手に取ることがある。ポール・オースターとか、スティーヴン・ミルハウザーなんかがそうだった。スティーヴ・エリクソンについても何も知らずに読み始めた。「ラテンアメリカ文学やサイエンス・フィクションを通過したフォークナー」(「訳者あとがき」)と評されるスティーヴ・エリクソンのスケールとパワーは、読むものを圧倒する。第二次世界大戦の勝敗が逆転した世界を描くフィリップ・K・ディックの『高い城の男』同様、スティーヴ・エリクソンの『黒い時計の旅』もまた史実と異なり、1945年を過ぎてもアメリカとドイツが戦争を続けている世界が描かれるが、『高い城の男』が戦後の新秩序下の状況そのものを群像劇として提示するのに対して、『黒い時計の旅』は、主人公バニング・ジェーンライトの数奇な人生が描かれ、世界情勢は後景にまで退いている。というか、目まぐるしく展開するエリクソンの小説世界では、見定めることより、むしろとめどない奔流に身を任せてしまうのがいいのだと思う。
魔術的リアリズムと称されるラテンアメリカ文学の大きなスケールと緻密な物語展開、もしドイツが負けなかったらというSF的設定、そして、時間や空間を超える壮大な物語の源泉に主人公がせっせと書き続けるポルノグラフィーがある。「書く」という行為が世界を作る、あるいは、書物が世界そのものだという発想は、ボルヘスの短編を思わせる。
これらは確かに『黒い時計の旅』の世界を特徴づける要素になっているが、やはり、柴田元幸が言うように、主人公の出生の秘密というモチーフはフォークナーを連想させるし、主人公の「孤児」的なありようは、アメリカ文学そのものだ。
事件を起こして、ニューヨークに出た主人公がポルノ小説を書き始め、その後、捜査の手から逃れるようにヨーロッパに渡り、ウイーンに腰を落ち着ける。彼が描くポルノの特別な読者というのが、ヒトラーとおぼしき人物だ。ヒトラーのために書かれるポルノグラフィーというのも実に奇妙だが、ヒトラーはその中にかつて唯一愛した姪にあたるゲリ・ラウバルの影を見出していたらしい。
失われた女、幻の女の影はさまざまな形で描かれ、『黒い時計の旅』の主要なモチーフの一つになっている。バニング・ジェーンライトもまた、自らが生み出した女を追っている。彼が書き継ぐという行為そのものが、物語の展開に大きくかかわってくる。彼はまた、ポルノグラフィーを使って、ヒトラーへの復讐を成し遂げようとする。
その復習が成し遂げられるのか、あるいは、何らかの形での救いがもたらされるのかといった、結末はさておき、20世紀そのものを失われたものだと仮定し、主人公が「書く」ことによって二つに引き裂いてしまった20世紀を再び回復しようとする試み、そして、二つの20世紀を行きかう複雑で異様な迫力がみなぎる物語を書き上げる作家の底力に驚嘆させられる。
『黒い時計の旅』という小説の魅力は、目の前に展開する時に生々しく、ときに幻想的な光景であり、それは読むという行為を通してしか得られない特別な体験だと思う。
余談になるが、ぼくが読んだのは白水Uブックスではなく、福武書店版のハードカバー。昔は福武文庫とか『海燕』という文芸雑誌も発行していていい出版社だった。